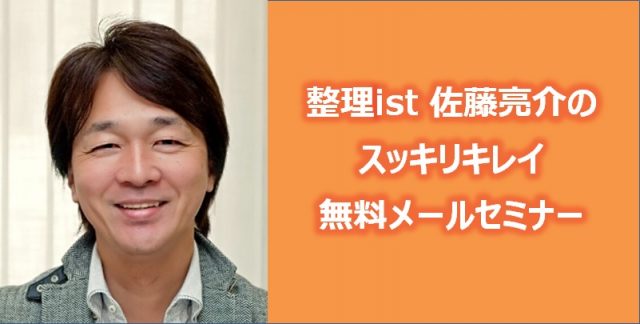整理収納アドバイザー1級の1次2次試験合格対策|男の整理収納アドバイザーが秘訣を伝授

今、整理収納アドバイザーは大変人気のある資格になっています。
整理収納アドバイザー有資格者数 累計:120,754名
*2級 112,117名 1級 8,367名(2018年10月現在)
私が2009年に整理収納アドバイザー1級の資格を取得した時には、1級の人数は1,000人にも満たない頃でした。
その後、この資格は女性を中心に人気が高まり、現在もすごい勢いで増えています。
整理収納アドバイザーの講座を受けるの多くは、自分自身が物だらけの生活に悩み、暮らしを変えていきたいということが一番の目的です。
一方、最初から自分も将来は整理収納アドバイザーというプロになって仕事をしてみたいという方もいらっしゃいます。
または、今の仕事に活かすためにとか、今持っている資格にプラスしてより活動の幅を広げたい、単純にいろいろな資格を取得したいなどの目的でチャレンジする方もいらっしゃいます。
いずれにしましても協会の規定で、整理収納アドバイザーというプロとして第三者への活動をする時には、1級の資格を取得することが義務付けられています。
ここでは、これから整理収納アドバイザーの1級にチャレンジしてみようかな?とか、試験前にどういう対策をしておけばいいのかな?とお悩みの方のために、私からいろいろなアドバイスをさせていただきます。
まだ整理収納アドバイザーの第一歩を踏んでいない人も、これからのためにぜひお読みになってみてください。
ただし、初めにおことわりしておきます。
具体的な試験問題は公表できません。
もしも、ネット上でそうしたことを公表している人がいましたら、その人は規定違反です。
そして、その人は整理収納アドバイザーとしてのモラルを欠いています。
試験問題は公表できませんが、それ以外の対策方法や心得をお話させていただきます。
これから受験される方には必ずお役に立てる内容ですのでご参考になさってください。
ハウスキーピング協会認定講師の私は整理収納アドバイザー2級認定講座を開催しています。
一日(約6時間)の受講で、必ずあなたも片付け上手になれるようにサポートいたします。
そして、同時に整理収納アドバイザー2級の資格も取得できる特典付きです!
毎月岡山で開催していますが、ご依頼いただけましたら全国どこへでも出向いて開催させていただきます。
詳しくは ↓ ↓ をクリックしてご覧ください。
目次
- 男の整理収納アドバイザー1級 整理ist 佐藤亮介
- 整理収納アドバイザー1級へのみちのり(ステップ)
- 整理収納アドバイザー1級を受ける人の心構え
- 整理収納アドバイザー1級の1次試験対策
- 整理収納アドバイザー1級の2次試験対策
- 資料作成は「実作業編」の方がオススメ!
- 作業の際に写真を必ず撮っておくことを忘れない!
- ただのビフォーアフター報告では低い評価になる!
- 整理収納アドバイザー理論や用語を無視しない事!
- 4つの領域図と収納の5つの鉄則は必須!
- 資料は簡潔にまとめること!
- 対象者(クライアント)との会話も必ず資料に入れておくこと!
- 資料や発表は他人にチェックしてもらいましょう!
- 時間配分、時間内に必ず発表は終わる事!
- 発表のスタートはゆっくりと大きな声で!
- 言葉遣い、きつい口調は禁物!つかみと笑いも重要!
- 身なり、服装、髪型、化粧なども観られています!
- 実際にセミナーや講演会に参加して勉強してみよう!
- 講師やプレゼン力を高めるために参考になる本
- ブログ著者 ロハスカタス 整理ist佐藤亮介のセミナー・講座・サポートのご案内
男の整理収納アドバイザー1級 整理ist 佐藤亮介

まずは自己紹介からさせていただきます。
本当に整理収納アドバイザーなのかどうかを信用していただかなくてはいけませんからね 笑
私は2009年に整理収納アドバイザー1級に合格し、翌年2010年に整理収納アドバイザー2級認定講座の講師として協会から認定されています。
全国的にも男の整理収納アドバイザーはまだまだ少ない中、ハウスキーピング協会の澤 一良副理事長の夢やポリシーに共感し、この世界に入りました。
圧倒的に女性の世界なので、今でも肩身の狭い思いをしていますが、少しずつ男性の受講者が増えてきているのは大変嬉しいです。
地道に活動してきたお陰で、明日香出版の女性編集者の目に留まり、本も執筆させていただきました。
整理収納アドバイザーで学んできたことや、いろいろな人や会社のコンサルタントで経験したことから、自分なりの「整理学」をこの本に書き綴っています。
お陰様で、中国、香港、台湾、シンガポールでも翻訳本が出版されています。
この私が本を書くなんて思いもよらなかったことです。
これも整理収納アドバイザーを受講し、整理収納アドバイザーになったお陰です。


テレビやラジオなどのメディアにも出演させていただいています。
日本テレビ「解決ナイナイアンサー」の相談員やAKB48の「俺の嫁選手権」、岡山地元のラジオ番組レギュラーなど。
こうしたことも私の人生には考えられなかったことが現実として起こっています。
全て、これも整理収納アドバイザーになったお陰なんです。
私のより詳しいプロフィールは下記をご覧ください。
整理収納アドバイザー1級へのみちのり(ステップ)

いくら自分が整理収納に自信があっても、いきなり整理収納アドバイザー1級の資格者にはなれません。
1級を取得するまでのステップがありますので説明します。
- ステップ1:整理収納アドバイザー2級認定講座の受講
まずは整理収納アドバイザーの登竜門として、整理収納アドバイザー2級認定講座を受講し2級のライセンスを取得しなければなりません。
2級の下に3級もありますが、3級は任意ですので2級からの受講で構いません。
個人的には3級をはじめに受けない方がいいと思います。
3級はどちらかというと「収納術」的な内容がメインですので、本当に整理収納について学ぶためには、または整理収納アドバイザーになるためには、2級の講座の基礎学習の方が大切だからです。
3級は2級や1級を取得してから受講される方がより役立つと思います。
整理収納アドバイザー2級認定講座は、講座の最後に簡単な試験があります。
いきなり2級から落ちたらどうしよう?って悩む必要はありません。
2級は1日受講していただければほぼ100%合格できます。
試験と云うよりも一日学んだことをまとめてみるという感覚でOKです。
心配ご無用ですのでご安心ください。
私は既に130回を超える整理収納アドバイザー2級認定講座の講師を務めています。
受講者も1,000人以上です。
今まで誰一人不合格者はいません。
少なくとも私の講座では絶対に不合格にさせない自信があります。
私の整理収納アドバイザー2級認定講座を受講希望の方は下記をご覧ください。
詳しくは ↓ ↓ をクリックしてご覧ください。
- ステップ2:整理収納アドバイザー1級予備講座の受講
整理収納アドバイザー1級に進むためには、まずは1級予備講座を受講しなくてはいけません。
いきなり1級の試験を受験することはできません。
整理収納アドバイザー2級認定講座の受講が終わりましたら、すぐに1級予備講座の受講を申し込むことができます。
2級の資格認定証は協会から届くのに約1ヶ月かかります。
認定証が届く前に1級予備講座を申込んでも構いません。
下記の協会ホームページに全国の開催日程や受講についての詳しい案内があります。
1級予備講座は連日2日間受講しなくてはいけません。
受講料は、32,400円(税込)
1級予備講座の案内と申込み
- ステップ3:整理収納アドバイザー1級1次試験
予備講座の受講が終了した人は、まず1次試験に臨むことになります。
ただし、中には資格が目的ではなく単純にもっと自分の整理収納の知識やスキルを高めたいために1級予備講座を受講するという方もいらっしゃいます。
その方は無理に試験を申し込む必要はありません。
予備講座を受講したから絶対に試験を申し込まなくてはいけないということではありません。
予備講座を受講し、しばらく経ってから将来的に受験する人もいらっしゃいます。
現在は予備講座受講から1次試験までの有効期間は無期限になっています。
ただし、あまり間をあけると折角勉強した内容を忘れてしまい、試験勉強が大変になりますのでご注意ください。
協会は2年以内を推奨しています。
1級1次試験概要
1次試験は、筆記試験です。
受験費用は、8,640円(税込)。
100問のマークシート形式で、90分間の時間制限になっています。
70点以上で合格
1問1点ですので、30問の間違いまでは大丈夫です。
協会によると、現在の合格率は70~80%になっています。
約1ヶ月後に合否の発表があります。
現在は郵送ではなく、協会のホームページで合格者の受験番号を発表しています。
自分で確認するのを忘れないでください。
万が一、インターネットが使えないなどホームページを見ることができない方は協会の事務局に問い合わせれば教えてくれます。
※電話番号:03-3465-3210
1次試験スケジュール 1級についてのよくあるQ&A
- ステップ4:整理収納アドバイザー1級2次試験
無事に1次試験に合格しましたら、次に2次試験に臨みます。
2次試験の会場は1次試験と違う場所でも構いません。
協会HPの2次試験の日程表を確認して申し込みましょう。
2次試験スケジュール
2次試験は、研究発表形式(プレゼンテーション)です。
受験費用は、10,800円(税込)です。
詳しくは、予備講座や1次試験の時に説明が行われます。
1級2次試験概要
受験の申込みを済ませたら、事前に研究発表のレポートを作成しなければいけません。
テーマは2パターンです。
下記のどちらかを選択してレポート作成を行ってください。
どちらが優位になるということはありません。
【提案型】
あなたが今後第三者(ご自身とご家族以外)に対して、整理収納においてどのような「提案」をしていくかを考えてください。
提案の方法を選択し、その方法に合った提案を制作してください。
【実作業型】
あなたが実際に行った(自身以外、家族可)整理・収納の体験を通して、その目的と効果を述べてください。
どのような目的で改善を行い、どのように理論を使いどのような効果があったかを具体的にしてください。
レポートは、A4用紙5枚まで(両面印刷の場合は10枚まで)と指定されています。
それ以上の枚数になっていると、そのページについては評価の対象にならないため不合格になってしまう可能性がありますのでご注意ください!
研究発表のレポート内容と当日の発表状況を総合して協会が合否を判定します。
当日は、3~5名ずつのグループに分かれます。(協会が任意に決めています)
各グループごとに部屋に移動し、くじ引きで決めた順番で一人ずつ前に出て発表を行います。
持ち時間1人20分間です。
各グループには、協会から認定された試験官が1~2名配置されています。
評価は試験官だけではなく、同じ受験者も1人ずつの発表に対して評価をします。
試験官の評価と受験者の評価を総合して、協会側が合否の判定を行うシステムです。
受験から約2ヶ月後に郵送で合否のお知らせが届きます。
万が一、1次試験が不合格になった人はもう一度1次試験を受験できます。
※予備講座から受け直す必要はありません。
万が一、2次試験が不合格になった人は2次試験を再受験できます。
※1次試験から受け直す必要はありません。
その他の詳細は下記をちゃんとご確認ください。
研究発表についての詳細
1次試験から2次試験までの有効期限はありませんが、モチベーションを保つためにも速やかに受験されることをおススメします。
下記のスケジュールをみてご都合の良い日程や会場をお探しください。
2次試験スケジュール 1級についてのよくあるQ&A
整理収納アドバイザー1級を受ける人の心構え

さて、整理収納アドバイザー1級への概要を知っていただけましたあなたには、いよいよ具体的なアドバイスに入っていきたいと思います。
まずは、これから整理収納アドバイザー1級にチャレンジしてみようと考えているあなたの心構えについてです。
折角その気になったのに水を差すことになるかもしれません。
だけど、とっても大切なことなので落ち着いて話を聴いてください。
もう一度、冷静になって、よーく考えて、自分自身の意志を確認してほしいのです。
【目的】
・あなたは、何のために1級を受けたいのですか?
・1級の資格を取得したい目的はなんですか?
【ビジョン】
・1級を取得したあとは何がしたいのですか?
・1級の資格をどう活かしていくのですか?
これらの目的やビジョンがはっきりと確定していないのでしたら、私はもう一度考えていただきたいのです。
もしくはやめた方がいいと思います。
ハッキリ言ってお金と時間の無駄遣いになってしまうからです。
ただ単に資格マニアになってはいけません。
今全国で約8,000人近い人が1級の資格を持っています。
私の整理収納アドバイザー2級認定講座の受講者の中からも多くの人が1級に臨まれて合格に至っています。
ただ、せっかくお金と時間をつかって取得した資格なのに何にも活かされていない人が多いのです。
本当にモッタイナイです。
とりあえず資格を取ったら何かに使えるかもしれないとか、仕事の依頼が舞い込んでくるかもしれないと曖昧な心構えではいけないのです。
資格はあくまでも資格です。
難関の国家資格に合格した弁護士や医師でさえ、事務所や医院を開業した所ですぐに依頼者や患者は来ませんよね。
つまり、資格を取ったからと言ってすぐにお金を稼げるわけではありません。
大切な事は、自分が何のためにという目的と将来のビジョンを持っているかどうかです。
そして、その資格をどう活かしていくのか?
最初は活動の場がなくても、お金にならなくても継続していく覚悟ができているかが重要なのです。
私は整理収納アドバイザー2級認定講座の際にも、または1級を検討している方からのご相談時にも必ずこのことを申し上げます。
折角その気になっているのに、水を差したり、足を止めてしまうことにもなりかねません。
だけど、私はみなさんにお金と時間の無駄遣いだけはしてほしくないのです。
協会の認定講師としては不適格な人間かもしれませんが、これは曲げられない私のポリシーです。
もう一度、ご自分の目的とビジョンに向き合ってみてください。
1級はそれからでも決して遅すぎることはありません。
整理収納アドバイザー1級の1次試験対策

さて、心構えもできたあなたに1次試験に向けてのアドバイスをさせていただきます。
1次試験は筆記テストです。
100問のマークシート形式問題を90分間で終わらせなければいけません。
単純に割り算すると、1問あたり54秒です。
受験日、受験番号、氏名の記入、見直し時間を入れると、1問あたりの時間はもっと短くなるわけです。
つまり、1問にかける時間は思った以上に短いということです。
最初は特に緊張しているので、問題の文章も冷静に読めなかったりします。
いくつか私からアドバイスをしますね。
100点を取ろうとしないこと!
当たり前の事ですが、試験は落ち着いた者勝ちなんです。
高校の時、優秀な同級生がいたんですが極度の緊張タイプで結局2浪してしまいました。
人は初めての事には緊張してしまいます。
私が大学の時に吉田美奈子さんのバンドのギターリストとして、はじめてプロのステージに立つ機会を得た時には本当に口から心臓が出るくらいに緊張しました。
その時に、吉田美奈子さんからこう言われました。
あなたが今しなくてはいけないのは緊張ではなくて、プロとしての緊張感を持つことよ!
活を入れられたことで心臓のバクバクはありましたが、指はちゃんと弦を奏でることができました。
緊張しないために効果的な方法があります。
脳科学者の茂木先生から教えていただいた方法です。
人間の脳が緊張するのは、今の自分以上の能力を出そうと頑張るからだ。
今の自分にできる範囲でいい。
自分のハードルを無理に高めようとしてはいけない。
頑張らなくていいぞ!って自分に言ってあげなさい。
これを教えていただいてたお陰で、人前で話をするのが苦手だった私でも今は講師として成り立っています 笑
今までで最高2500人を前に講演をしたことがありますが、自分でも不思議なくらい落ち着いて話をすることができました。
だけど、時々講演やテレビなどでちょっといいことを話してやろうとすると緊張してしまいます。
やっぱり、無理いちゃいけないんですね。
自分の力量を超えて頑張ろうとするといい結果は出ないです。
1次試験は70点以上で合格です。
30問間違えても合格できます。
100点を狙う必要はないのです。
100点の人と70点の人で、評価やその後の何かが変わるのかと言えば何にも変わらないのです。
自分のハードルを無理に上げてしまうことだけは絶対にやめましょう!
満点を狙わず、気軽な気持ちで1次試験に臨まれてください。
分からない問題はすぐに飛ばす!
先程お話したように、1問あたりの時間は短いです。
分からない問題に時間をかけるのはやめて、すぐに次の問題に飛ばしていきましょう。
ただし、あとでもう一度見直す際にすぐに分かるように、飛ばした問題の番号にはチェックを入れておきましょう。
何度も言いますが、70点取ればいいんです。
緊張や焦りから解放されるためにも、無駄に時間を使うよりも飛ばしていった方が賢明です。
ひっかけ問題に注意!
澤副理事長には怒られるかもしれませんが、澤先生は優しい人ですが「ひっかけ」も好きです。
でも、大抵のいろいろな試験問題には「ひっかけ問題」は付き物です。
運転免許の〇×試験だってそうです。
「近くのコンビニくらいだったらスリッパで運転しても構わない」
「運転免許証はカラーコピーだったら不携帯にはならない」
1次試験はマークシート形式なので、選択肢が5つあったりすると余計にひっかかりやすいので気をつけましょう!
例えばこんな感じです。
※これは実際の問題ではありません。
プロパティとは以下の中から正しい物を選びなさい。
・自分が持っている全ての物
・ただ持っているだけで活用されていない物
・自分が気に入ってよく使っている物
・思い出が深く大切な物
・捨てたくても捨てられない悩んでいる物
答えは2番目ですよね。
選択肢が多ければ迷いやすくなります。
そこで大切な受験対策は・・・
テキストを何度も何度も読むこと!
当たり前ですが、1次試験の受験対策は復習しかありません。
2級のテキストと1級のテキストから出題されますので、この2冊を何度も繰り返し読むことが一番重要です。
暗記しようと頑張らずに小説を読むようにただ読んでください。
ただ1回だけだと忘れてしまいますので、何回も読むことが大事です。
特に、整理収納アドバイザーで使われている特別な用語がありますよね。
スマイルマーク、アクティブ領域、スタンバイ領域、グルーピング収納、定位置管理などの用語の意味は絶対に暗記しておきましょう。
そして、正しくテキスト通りに覚えましょう。
ここがすごく大事な部分です。
自分なりに解釈したり、いい加減に漠然と覚えている人が「ひっかけ問題」に引っかかりやすいのです。
設問は全般にわたって出題されますのでヤマ勘や傾向と対策はありません。
とにかく2冊のテキストを最初から最後まで全部読みこむしかありません。
常に手の届くところにテキストを置いて、時間がある時だけでもいいので読む習慣を身につけてください。
ベッドの枕元、通勤中に、お昼休みに、いろいろな隙間時間こそが有効な時間です。
人は限られた時間がある方が集中できます。
だらだらと読むよりも、たとえ5分でも集中して読む方が記憶になりやすいのです。
家族や友人に問題を出してもらいましょう!
ある程度読むことができたら、家族や友人などにテキストを渡して適当に問題を出してもらいましょう。
その人が整理収納アドバイザーを勉強したことがない人だったらよりいいです。
固定概念や先入観がありませんし、本当にその人が分からないことを出題してくれるからです。
誰かに頼むのが難しい場合には、協会が有料で提供しているアプリを活用するのがいいでしょう。
スマホやタブレットに下記のアプリをインストールしてお使いください。
200問以上の例題を試してみることができます。
ただし、ここに出ている問題がそのまま出題れるとは限りませんし、このアプリさえやっておけば大丈夫って甘く考えていると本番で失敗してしまいます。
あくまでも練習としてアプリは活用なさってください。
こんな感じの問題がでるのかっていう程度にしてください。
【協会が用意している有料アプリ】
iPhone版インストール アンドロイド版インストール
整理収納アドバイザー1級の2次試験対策

整理収納アドバイザー1級試験で一番の難関が2次試験です。
多くの人はここで壁にぶつかります。
と言っても、合格率が低いと云うことではなく、研究発表のレポート作成に悩んだり、人前でプレゼンをすることに不安をかかえる人が多いという意味です。
確かに今までプレゼン資料や発表の経験がない人には不安になる気持ちはよく理解できます。
でも、そんなに難しく考えないで下さい。
コツさえつかめば大丈夫ですから。
資料作成は「実作業編」の方がオススメ!
2次試験の研究発表は、「提案編」と「実作業編」のどちらかを選択します。
「提案編」は、いわゆる第三者へのコンサルタントです。
物の整理で悩んだり、捨てられない人などに対してどのようにアプローチを行い、解決へと導いていくかをまとめて報告するものです。
条件の中に「自分と家族以外に対して」とありますので、コンサル経験のない人にはかなり難しいと思います。
コンサル力は知識や空論よりも実経験でしか高めることはできません。
コンサル力は1級に合格し、その後いろいろな経験をする中で自然と身につけていきましょう。
「提案編」と「実作業編」で評価の優位性はありませんので、とにかく自分が作りやすいと思える方を選べばいいのです。
そういう意味から、私はコンサル経験のない人には、「実作業編」の方が資料も作成しやすいと思います。
条件として、自分の物や場所のビフォーアフターではダメになっています。
家族や友人、実家や親戚などにお願いして実際に整理収納の作業をしてください。
この「実作業編」の方が、資料も作りやすいと感じませんか?
ただ、いくつかコツがあります。
作業の際に写真を必ず撮っておくことを忘れない!

結構多くの人が失敗するのが写真の撮り忘れです。
作業に夢中になってしまい、大事な写真を撮っておくのを忘れてしまうのです。
文章だらけの資料と写真付だったら、あなたはどちらが読みやすいですか?
写真が載っていると分かりやすいし、長めの資料でも読みたくなるものです。
特に、ビフォーアフターを説明するのに写真で見せる方が一目瞭然ですよね。
あとで、シマッタ!って思っても遅いです。
どうしても写真を残しておきたいって、また元通りにして作業のし直しってことにもなりかねません。
普段から、何か作業をする時にはスマホを携帯して写真を撮る癖をつけておきましょう!
もうひとつ写真を撮る時の大事なコツがあります。
多くの人は、作業前のビフォーと作業後のアフターしか撮らないのです。
後ほどもお話しますが、大事なことはビフォーアフター以上に途中経過です。
ビフォーの状態が、どういう作業過程を経てアフターの状態になったかの方が重要なんです。
ですので、写真は途中の過程も必ず撮っておくべきです。
必ず資料作成の時や発表の時に役に立ちますから。
ただのビフォーアフター報告では低い評価になる!

テレビや雑誌に多く見られるビフォーアフターに惑わされてはいけません。
整理収納アドバイザーの2級や1級講座で学ばれたように、私たち整理収納アドバイザーはただの「収納」のプロではありません。
特に、収納技や収納グッズのオンパレードの報告では評価はもらえないと思って下さい。
私たち整理収納アドバイザーは、「整理」⇒「収納」へと導いてさしあげるプロなのです。
つまり、「整理」というステップを絶対にはずしてはいけません!
服が溢れているクローゼットがあって、その服たちをその人と一緒にどうやって整理していったのか。
そして、その後何をポイントにして収納を作り上げていったのか。
「途中の過程」こそが、整理収納アドバイザーの一番大事なポイントです。
整理収納アドバイザー理論や用語を無視しない事!

繰り返しますが、あくまでもあなたが試験を受けようとしているのは整理収納アドバイザーの資格です。
断捨離でも、こんまりの片づけでも、自分流の整理収納法でもありません。
もしも、自分流の方法をアピールしたいのでしたら、1級の資格を取得してからです。
車の教習所で、自分はハンドルをこうやった方が回しやすいとか、片手の方が縦列駐車しやすいからってやってたら不合格になりますよね。
整理収納アドバイザーの資格を取るわけですから、あくまでも整理収納アドバイザーの理論に沿って作業を行い、資料にまとめるようになさってください。
間違っても、「まず収納用品を買いに行き、それから物の整理をやりました」なんていう順番は最悪の評価をされてしまいます。
そして、用語も大切です。
整理収納アドバイザーの理論には、いろいろな専門用語がありますよね。
「スマイルマーク」を「ニコニコマーク」とか「ピースマーク」みたいに勝手に自分で変えてはいけません。
私は「グルーピング収納」のことを「お友達収納」とか、「定位置管理」を「物の住所決め」などと言い換えていますが、それは資格を取得してからのステップです。
2次試験の時は、試験官以外に同じ受験者もあなたの資料や発表を評価します。
言葉ひとつひとつにも間違いがないか聴いていますのでご注意なさってください。
4つの領域図と収納の5つの鉄則は必須!
整理収納アドバイザーを受講したあなたでしたら、「4つの領域図&パターン1~4」と「収納の5つの鉄則」は聞き覚えがありますよね。
2次試験のための実作業では、絶対にこの2つを欠かしてはいけません。
整理収納アドバイザーは、これが生命線と言っても過言ではありません。
例えば、あなたが実作業する場所や物の状態は「4つの領域図」のどのパターンですか?
それがハッキリと分かれば、あとは8つのステップに基づいて作業を進めていくだけです。
そして、今度は収納を考えていく中では「5つの鉄則」をきちんと盛り込んでください。
この5つの鉄則に基づかない収納は、整理収納アドバイザーの理論から外れてしまいます。
こうした整理収納アドバイザーの理論が、所々にちゃんと盛り込まれているのかが、資料や発表の評価基準になります。
絶対に忘れないようになさってくださいね。
資料は簡潔にまとめること!

試験官として資料を拝見する時に、いきなり最初から残念だなって感じることがあります。
それは、資料の文章がダラダラと長いために読みにくい、見にくいということです。
折角、いい内容なのに読む気がしないという時点で大きなマイナスポイントです。
あれもこれも書きたい、伝えたいという思いは分かりますが、それはジコチュウの思いです。
相手にちゃんと伝わらなくては資料も発表も意味がなくなります。
中には、自分が発表をする時に話す内容をまるでドラマや映画の脚本のように書き綴っている人がいます。
これでは、読む人は資料を見た瞬間に嫌気がしてしまいます。
ハッキリ言って、受験者は資料を見る余裕はあまりありません。
発表者の評価をたくさんの項目別に記入していかなくてはいけないからです。
つまり、発表こそが評価の大部分です。
資料は簡潔に、箇条書きなどを用いて読みやすく、分かりやすくまとめるようになさってください。
終始下を向いて資料を読んでる人と、資料には時々目を落とす程度でほとんど前を向いて話をしている人。
あなたはどちらの人を高く評価をしますか?
前を向いて話をしている姿だけでも自信たっぷりで高評価にしたくなるはずです。
資料をまとめる力もプロとして成長していくためには大切なポイントです。
対象者(クライアント)との会話も必ず資料に入れておくこと!

あなたがその人とどれだけ寄り添ったか?が、資料にも発表にもちゃんと盛り込むことを忘れないでください。
整理収納アドバイザー2級認定講座で、一番最初に学んだことを思い出しましょう。
「目的」や「目指していること」を明確にすることが最初に大切だと教えられましたよね。
あなたが実作業をしていき、それを資料にまとめるにあたって、クライアントになっていただく相手の人とその会話を行っているかどうかは大変重要なポイントになります。
これは、整理収納アドバイザーとしての自覚が問われる部分です。
いきなり物の整理の作業から始めました。ではよくありません。
そして、作業中の相手とのやりとりもちゃんとメモして資料や発表には盛り込んでください。
前述の通り、ビフォーアフターも大事ですが、それよりもっと大事なことは途中の過程です。
どういうやり取りをして、その人はどういう風に変わっていったのか?
最初は物の整理に時間がかかっていたけど、次第に早くなっていったのはどういう気持ちの変化があったのか?
そして、最後も重要です。
使い勝手の良い収納が完成しました!で終わってはいけません。
その収納が完成して、または生活してみて、その人はどういう感想をおっしゃったのでしょうか?
それに対して、あなたはどう感じたのでしょうか?
こうしたクライアントの側に立って、寄り添って、一緒に解決していった経過を報告する内容にまとめてみてください。
発表を聴く側も最後がはっきりとしていることで納得できます。
起承転結の流れを忘れないようにしてください。
資料や発表は他人にチェックしてもらいましょう!

自信を持って発表をするためには、一にも二にも前準備です。
資料がある程度できましたら、家族や友人に読んでもらいましょう。
正直に言ってくれる相手の方がいいです。
お世辞や甘い言葉よりも、あえて辛口に評価してくれる方がいいんです。
「ちょっと文章が長すぎない?」
「ここの部分が読んでもよく分からないね」
「ここには写真があった方がよくない?」
そして、評価してもらう人は1人よりも2人、3人と多い方がいいです。
家族よりも友人や職場の同僚や上司など他人の方がいいです。
だって、試験官や受験者は他人なのですから。
いろいろな人に評価してもらった方がより実践的な資料にまとまるはずです。
発表の練習も場数が勝負です!
当日、あがらないためにも発表の練習を何度もおこないましょう!
自分一人でするよりも、家族や友人などを前にして実際に発表をしてください。
この時も遠慮なく助言してくれる人の方がいいです。
厳しいことを言われて気分を悪くしないで下さい。
その人はあなたのためにちゃんと考えてくれている証拠ですからね。
「声が小さくて聞き取りにくいよ」
「早口になっているよ」
「ここのとこが分かりにくかったね」
資料も発表もこうした人の意見をもとにして修正していくのです。
恥ずかしいとか面倒くさいって思ってはいけません。
これも整理収納アドバイザーになるための大切なステップなのです。
第一、実際にプロになって活動していく中では他人と話をしたり、作業をしなくてはいけません。
コミュニケーション力の練習だと思ってください。
試験官も同じ受験者もお客様の立場や視点で、あなたを見たり聴いたりしています。
自分が依頼主のクライアントだったら、この人に家の片づけを手伝ってもらいたいと思えるかということです。
もう一度申し上げておきます。
資料や発表は人に見てもらう、聴いてもらうことを絶対に忘れないで下さい。
特に、発表の練習は場数が合否の明暗を分けます!
時間配分、時間内に必ず発表は終わる事!

発表の練習をする時に、もうひとつ重要なポイントがあります。
それは「時間」です。
発表は一人当たり20分までと決められています。
20分の時間内にちゃんと納めなくてはいけません。
5分前には試験官から合図が出ます。
そこで多くの人は焦ってしまって、早口になったり、本当は話すはずだった部分を飛ばしたりします。
そうなっては、試験官にも受験者にもバレバレなので評価にも影響してしまいます。
最悪なのは時間内に終わらず、尻切れトンボになってしまうことです。
「あとは資料をご覧になってください。」
これって、まとめることができない人なんだ、練習不足なんだって自分でバラしてしまっているようなものです。
そもそも、試験官も受験者も自分の評価票を記入するのに必死ですから、「ご覧になってください」って言われても読む余裕なんてありません。
練習をする時には、時計を見ながら時間配分もチェックしておくようにしてください。
または誰かに時間を見てもらう方が話に集中できていいかもしれません。
ここまで10分以内におさめよう。
このペースでは時間オーバーになりそう。
そして、練習の時は15分で終わるようにしておくのがいいです。
本番ではどうしても緊張したりして時間が延びやすくなりますから、15分で練習していけばちょうどいいくらいになります。
たとえ本番でも5分前に終わったとしても、無理に長引かせようとせず「少し早いですが以上で私の発表を終わらせていただきます。」でいいです。
時間内に終わらない人と、少し早めだけど終わった人では、聴いているあなたの印象はどちらが高評価になりますか?
時間内にきちんと終わらせるってことは大変重要なポイントなんです。
発表のスタートはゆっくりと大きな声で!

トンネル内の事故は出口で多いと言われています。
それは出口のヒカリが見えると、人は早く出たいという意識が働くので無意識にアクセルを踏んでしまい追突事故を起こす可能性が高いのだそうです。
それと同じで、人前で話をするのに馴れていない人は早く終わりたいという意識が高まります。
そのため、口調と云うアクセルを踏んでしまい早口になりがちなのです。
おまけに早口になると声も小さくなります。
人は大声で早口は訓練しない限り無理なんです。
そこで、練習の時も含めて2つのコツを伝授します。
・話しはじめは、意識的にゆっくり目の口調
・大きな声でスタート
皆さま、こんにちは。
今から発表をさせていただきます〇〇と申します。
どうぞ宜しくお願い致します。
これをゆっくりと大きな声でスタートしてみましょう。
これをすることで自分のペースをつかむことができます。
大きな声を出すことで気持ちも落ち着きます。
ぜひ、練習時から取り入れてみてください。
言葉遣い、きつい口調は禁物!つかみと笑いも重要!

人の話を聴いてて一番嫌悪感を感じるのは、上から命令口調で言われる時ではないでしょうか?
「私はこう思うから、あなたもそうでしょ?」
これは共感を強制的に促している感じに受け取られやすく、聴いてる側は耳を閉ざしてしまいます。
または、馴れ馴れしい言い方やタメ口っぽいのも禁物ですよね。
初対面の方に発表をする際に、そういう言い方をするということはクライアントの人にも同じように接するのでは?と感じられてしまいます。
「私はこう思うの。皆さんも同じじゃないですか?」
↓
「私はこう思います。皆様も同じではないでしょうか?」
それから、「つかみ」が大事です。
漫才師は最初の3分間でお客様の気を引かなくてはウケないそうです。
この最初の出だしを「つかみ」と言います。
人前で話し馴れていない人には少しハードルが高いかもしれませんが、このつかみがあるとないのでは聴く側の評価は大きく変わります。
あまり難しく考えず、簡単なつかみでも充分です。
たとえば、私はこういう「つかみ」があります。
こんにちは。
収納が苦手な整理収納アドバイザーの佐藤です。
でも、整理は得意なので整理ist の佐藤と覚えて下さい。
えっ、収納が苦手ってこの人、整理収納アドバイザーじゃないの?
そもそも、収納が苦手で整理は得意ってどういうこと?
お客様はここで不思議なことを言う私に興味を持ってくれます。
そして、整理と収納がどう違うのか?と疑問を抱いてくれます。
聴く側にこれからの話を聴いてもらえる心の準備をしていただくわけです。
「つかみ」は難しくありません。
ウケようとか、笑わせようとか考えなくて、自己紹介の時に少し工夫してみるだけでもいいのです。
皆さま、はじめまして。
〇〇から来ました〇〇と申します。
今朝は晴天で、頑張っておいでって背中を押してもらった気分です。
どうぞ宜しくお願い致します。
こんな感じでも、聴く側の心を充分につかめるはずです。
ただし、ネガティブなことは言わないようにしましょう。
人前でプレゼンするのは初めてです。
ちょっと緊張していますが頑張ります。
あまり練習していないので聞き苦しい点はお許しください。
聴いてる側もほとんどの人が初めてですし緊張もしています。
相手の気持ちが暗くなるようなことは言わない方がいいです。
むしろ、天気がいいとか、今朝こんないいことがありましたとか、気持ちが明るくなるような「つかみ」を心掛けて下さい。
身なり、服装、髪型、化粧なども観られています!

2次試験のプレゼンの時には、身なり、服装、髪型、お化粧などにも気をつけた方がいいかもしれません。
私が受験した当時は男性はほとんどいなく、女性の中でのプレゼンでした。
アウェイな感じがして、女性には厳しく評価されるかもしれないな~って思いました。
だけど、女性に訊いてみるとそれは逆だそうです。
女性は同姓に対しての方が厳しい目で観ていることが多いのだそうです。
服装やアクセサリーが派手とか、化粧が濃すぎるとか、髪がボサボサだとか。
決して、パーティに出かけるようなドレスアップは必要ありませんが、清潔感のあるコーディネイトの方がいいでしょうね。
やはり、白を基調に派手なカラーや混色は避けるべきでしょう。
少なくとも、デニムにTシャツ、スニーカーみたいなラフすぎる服装、革ジャン、ジ―ジャン、迷彩色など攻撃的な服装は絶対にやめるべきです。
当日のコーディネイトや髪形なども、家族や友人に事前に見てもらってチャックしておく方が賢明です。
実際にセミナーや講演会に参加して勉強してみよう!

機会をつくって人のセミナーや講演会に参加するのもオススメです。
ただし、大学教授や科学者、政治家などは当たり外れがありますので避けた方がいいかもしれません。
結構、自分の研究や考えを押し通すタイプの人の話は、聴く側のことは二の次にしているので上手ではありません。
テレビでお馴染みの人で話し上手な人や、講師業を専門でやっている人とかは大変参考になります。
話し方、メリハリの付け方、視線の気配り、つかみ、質問の出し方などに着目して、真似をしたいことなどをメモして帰りましょう。
私は今でも、いろいろな人の講演会に参加します。
興味のあるジャンルばかりじゃなく、聴いてて内容はよく理解できなくてもいいのです。
話の内容よりも、その人から何か盗めないか?参考にできることはないか?に力点を置いているからです。
最寄りの公民館や自治体が開催しているセミナーや講演会は結構頻繁に行われています。
ネットで、例えば「岡山市 講演会」とか「岡山 掃除セミナー」とかで検索してみると見つかりますよ。
講師やプレゼン力を高めるために参考になる本
本を読むのもいいですね。
なるほど、なるほどって参考になる事がたくさん書いています。
私が読んでみた中で面白かった本を2冊ご紹介しますね。
大谷由里子さんの「講師を頼まれたら読む本」は、とても面白くて参考になることも多かったです。
大谷さんは吉本興業でマネージャーをされていた経験をお持ちで、聴く人の心をどうしたらつかめるのかを教えてくれています。
松尾昭仁さんは、そもそも講師になるとは自分でも思っていなかった人ですが、今では人気講師として全国で大活躍なさっています。
初心者目線でいろいろと教えてくれている1冊なので大変参考になります。
以上、協会や澤先生から注意されない範囲でノウハウをお話させていただきました 笑
これから整理収納アドバイザーを志されているあなたのお役に立てましたら嬉しいです。
私は日本中や日本人がもう一度昔のように、無駄な物を持たないスッキリキレイな暮らしを取り戻していってほしいと願っています。
本当の豊かさや幸せとは何なのかを見つめ直してほしいです。
そのために、ちっぽけな存在ですがお役にたてるよう励んでいます。
あなたもぜひ整理収納アドバイザーの仲間になっていただき、未来の子供たちのためにキレイな日本を取り戻す活動をしていただけませんか?
またどこかでお会いできますこと楽しみにしております。
最後までご購読いただきましてありがとうございました。
よし、とりあえずは整理収納アドバイザー2級認定講座から始めよう!と思われた方は、↓ をポチっとしてご覧ください。
お役に立てましたらポチッと応援をお願いいたします!
↓ ↓ ↓
私の無料メールセミナーは、整理収納アドバイザー2級認定講座の予習や復習にも活用されています。
宜しければご参加ください。
ブログ著者 ロハスカタス 整理ist佐藤亮介のセミナー・講座・サポートのご案内
下記のページをご参照ください。