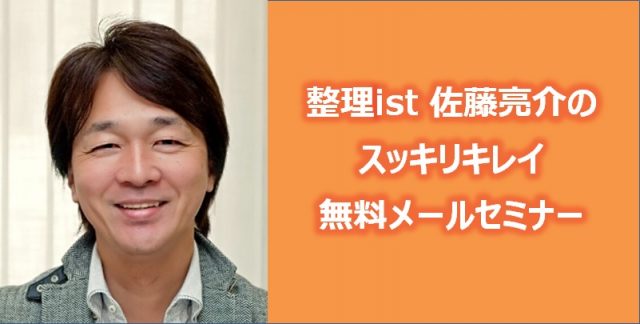汚部屋、モノだらけをスッキリ・キレイにできる片づけや掃除のコツをプロがアドバイスします!

キレイにしたい、キレイにならないとお悩みのあなたへ
おそらく、あなたはもう分かっているのかもしれません。
もうすでに気がついているのかもしれません。
原因が分かっているのに上手くいかないのはなぜ?
キレイにし始めても長続きできないのはなぜ?
一旦キレイにしてもまたリバウンドしてしまうのはなぜ?
多くの人が悩み、答えが見つからないのは正しく学び、身につけていないからです。
「正しく」とは、結果を出せるということです。
そして、もうひとつは継続性・習慣化です。
継続性や習慣化のために一番必要なことは≪やる気≫のスイッチです。
そして、その≪やる気≫のスイッチを入れるのに必要なことは≪楽しい≫、≪おもしろい≫、≪タメになる≫です。
私の整理ist としての活動は≪ 3S ≫です。
- 整理
- 掃除
- 洗濯
の頭文字のSをとって3Sと呼んでいます。
私たちの暮らしや身の回りをキレイにしていくために必要なことはこの3つのSだと考えています。
皆様の心を動かし、やる気スイッチをONにしてさしあげられることができれば幸いです。
少しずつ記事を書き足していきます。
次にココを開いた時にはまた新しい記事が増えているかもしれません。
どうぞ末永くお付き合いくださいね。
では宜しくお願いいたします。
目次
整理、片づけ、掃除は何のためにするのか?目的と目標を決めることが大切です!

何事もそうですが、1からスタートしなければ2、3へと進めません。
たぶん、ほとんどの方がいきなり自転車にまたがって乗れるようになった人はいないはずです。
そして、自転車に乗りたいと思った目的や目標があったはずですよね。
話は変わりますが、私は2年前から初詣に行くようになったんです。
多くの方の初詣の目的は、「願かけ」だと思います。
無病息災、受験に合格しますように、彼氏彼女ができますように・・・
だけど私の初詣はもちろんお願い事もありますが、それよりももっと楽しみにしている目的があるんです。
それは「屋台の食べ歩き」なんです(笑)
普段お祭りや花火大会に行かない私には珍しくて、美味しくて、楽しいんです。
私の初詣は「屋台の食べ歩き」が1番の目的になっています(笑)
このように目的や目標は人それぞれ違います。
これは、整理・片づけや掃除にも当てはまります。
私はお客様や受講者の方にまずはこの「目的や目標」を明確にしていただきます。
「何のために家や職場をキレイにしたいのか?」
「キレイしてどうしたいのか?」
「どういう暮らしをしたいのか?」 など。
この目的や目標が、ただ単に「家をキレイにしたいから」だけでは、モチベーションや継続性が維持できないんです。
もっと具体的に決めた方がいいのです。
なぜキレイにしたいのか?目的・目標というストーリーを考えてみてください。
以前、家の整理をお手伝いしたお客さまのお話です。
その方はご主人との関係が最近ちょっとこじれていました。
ある日、昔の写真を見たときに、
新婚の頃の思い出がよみがえってきたそうです。
二人ともすごく笑ってて幸せそうだったそうです。
そしてその写真には、
新婚生活が始まったばかりの家の中が写っていたそうです。
それを見た時に、その方は家の中を
あの頃のモノが少なくてスッキリ・
キレイな状態にもう一度戻してみたくなったそうです。
それが私に依頼をされた目的でした。
今年年賀状をいただきまして、
そこには二人でハロウィンでお化けに
仮装している写真が載っていました。
その写真でその方のお悩みは解消されたんだなって感じました。
他にも、ある若い女性が私の整理収納アドバイザー2級認定講座を受講しにいらっしゃった時のお話です。
その方がなぜ受講しようと思われたのかと
言うと、5年ぶりに彼氏ができたそうです。
前の彼氏にふられた理由が、片づけだったそうです。
片づけが苦手で、
自分の部屋はいつも散らかっていたそうです。
ある日、彼氏が遊びに来て、
その部屋を見てふられてしまうきっかけになったとか。
それからも片づけは苦手なままできた
けど、またふられるのはショックだし、
もしも結婚となると、将来の子供のため
にも今から自分を変えていこうと決めたそうです。
ステキな奥さんになりたい。
素敵なママになりたい。
それがその女性の目的や目標でした。
このように、
- 自分は何のために整理をしたいのか?
- どういう暮らしや生き方をしたいのか?
- キレイになった時あなたはどうなっていますか?
自分なりのストーリーを考えてみることが大事だと思っています。
皆様にもこうした目的・目標と言うストーリーを考えてほしいです。
それこそが、本当の願かけなんじゃないでしょうか?
整理や片づけは「忘れる」と「忘れない」ためにすることです!

今日は2017年4月12日です。
入学や新学期の子どもたち、新入社員の皆さんは、これから毎日いっぱいいろいろなことを学び、覚えていかなくてはいけませんよね。
だけど、人はすぐに忘れてしまうことの方が多いんです。

片づけても忘れる理由|脳はすぐに忘れる。記憶には優先順位がある。
エビングハウスの忘却曲線によると、1時間後には56%忘れ、1日後には74%忘れるらしいです。
私も歳をとってきて、あれ・それが多くなってきました(笑)
そもそも脳は「忘れる」ことも大切な働きだと言われています。
そして、記憶には優先順位が決まっているとも言われています。
私たちは毎日、膨大な情報が入ってきてそれらを全部覚えてられないんです。
優先順位を決めて、できるだけ無駄なことは忘れて、必要な情報だけを脳は入力しなければいけないわけです。
自分が持っている物や物をどこに置いたか?収めたか?は、脳はそれほど重要にしていないのです。
だから、すぐに忘れてしまうのです。
そして、一度に記憶できるのは、3つから4つまでだそうです。
傘を置き忘れるのは他に覚えなきゃいけないことがそれ以上あって、脳みそからこぼれてしまっているんでしょうね(笑)
“私のスマホはどこに行ったの?”
“カギがいつも行方不明になるんだよね”
ってよく耳にしますが、物は自分で勝手にどこかに行くことはありません!
片付けの効果|習慣化した体はちゃんと覚えている。
片づけが得意な人は忘れ物が少ないと思います。
それは、自分が使った物を元あった場所にきちんと戻す習慣が身についているからです。
物の置き場所を決めてて、使い終わったら元に戻すのでいつも同じ場所にあります。
そういう人は、いちいち物をどこに置いたかはすぐに忘れているんです。
物の定位置が決まっているので忘れてもいいんです。
だけど、習慣化した体はちゃんと覚えているんですよ。
例えば、あなたは朝歯を磨いた後、歯ブラシや歯磨き粉をどこに置いたかなんていちいち覚えようとしていないですよね。
だけど、毎朝捜すことはしていないですよね。
一旦は忘れるけど、体はちゃんと覚えている。
これが「片付けの習慣化」による一番の効果です!
物が少なければ、持っている物を忘れても、忘れない
脳科学者の茂木先生にお聞きしましたら、置き場所まで含めて記憶できる物の数は、150~300アイテムだそうです。
一方、今の日本人は平均で約3,000アイテム持っています。
一般的なコンビニ1軒分です。
完全に、脳のキャパオーバーという状態です(笑)
整理・片づけは安全安心な家をつくることも大きな目的です!

日本の家の中は危険だらけ!ヘルメットと安全靴が必要かもしれない家とは?
今年2017年で日本大震災から6年を迎えます。
阪神淡路大震災は22年が経ちました。
昨年は熊本でも大きな被害にあわれた方がいらっしゃいます。
岡山も鳥取を震源地にした地震で県北の方は被害にあっています。
その他、豪雨で堤防が決壊したり、竜巻、土砂崩れなど日本だけじゃなくて世界中で災害が発生しています。
さらに私はよく講演会で、
「今の日本の家は、家の中でヘルメットと安全靴を付けていないと危険な状態です」とお話しているんです。
例えば、「バリアフリー」という言葉がありますよね。
多くの方は、
- 段差を無くしたり、
- 廊下を広くしたり、
- 手すりをつけたり・・・、
そういう家のイメージだと思います。
でも、多くの家は家の中の構造だけをバリアフリーにしているだけです。
本当に安全なバリアフリーになっていないんです。
バリアとは障害物、フリーとはそれを無くすという意味です。
だけど私が考える障害物は段差や狭い廊下ではなく、モノが障害物なんです。
いくら構造をバリアフリーにしたとしても、床や廊下にモノが置きっぱなしや散らかった状態では安全ではないですよね。
地震をはじめ、いろいろな災害の時には普段私たちが使っているモノたちが凶器として襲ってくるわけです。
バリアフリーも地震対策をしておくのもいいことです。
避難用品の準備も大事なことです。
だけど、その前に家の中は本当に安全なのか?
自分だけじゃなくて、家族の安全をもう一度考えてほしいのです。
その第一歩が、私はモノの整理・片づけだと考えています。
あなたの家の床は安全な状態ですか?

床や廊下や階段にモノが置きっぱなしになっていないでしょうか?
玄関がモノだらけですぐに避難できますか?
そして、とりあえず今日すぐにこれをチェックしてほしいのです。
あなたの家の中の上を見上げてみて安全チェック!


頭より高い場所に物を置いていないかです。
特に落ちてきて、ケガや命にかかわるような危険なモノがないでしょうか?
多くの家でタンスや食器棚、本棚などの上にモノを置いています。
あの場所は棚ではありませんので、モノは置いてはいけないんです。

または、キッチンの吊戸棚の中もそうです。
結構、吊戸棚の中を見ると、ホットプレートや卓上コンロ、土鍋、使っていない食器といった危険物がいっぱいです。
それらが落下して、もしも頭を直撃したら一巻の終わりです。
そういう意味で、私はヘルメットをかぶっていなければ危険なのかもと申し上げているわけです。
もう一度、モノの整理をしてください。
少なくとも、危険なモノを上から下へと置き場所を変えてください。
安全な収納の仕方や方法があるのでご紹介します。
- 底の厚みのあるコップは上向きに立てた方が倒れにくいです。重心が下の方がいいわけです。
- お皿を積み重ねる場合は、下から言うと、大皿・小皿・中皿がいいです。真ん中の小皿が揺れを軽減してくれるそうです。
- 包丁、ナイフ、フォークなどの収納にも注意してください。包丁はシンクの上に置くのは危険です。ナイフやフォークも床に落ちると危険です。食器棚の引出しに入れている場合は、輪ゴムなどで縛っておくと落下した時もバラバラになりにくいです。
掃除の間違い|正しい掃除の方法やコツをアドバイスします!

誰がそんな掃除を教えたの?
私は掃除の講師としても活動しています。
多くの女性をアドバイスしてきましたが、ほとんどの方が間違った掃除の仕方をしています。
誰が教えたのか?
誰からそう習ったのか?
我流でそうしているのか?
日本人は世界一のキレイ文化を持っていました。
だから掃除も得意でした。
でも、いつしかその正しい掃除の教えや文化が我が子へと伝承されることがなくなっています。
親や大人が正しい掃除の仕方を知らないのですから子どもたちは間違ったやり方をしてしまうのは仕方がありません。
掃除の具体的な方法については別の「掃除」のページをご参照ください。
↓ ↓ ↓ ↓
https://www.kireiseikatsu.com/category/souji-jyutsu/
えっ、そうだったの!目からウロコの掃除のコツ

-
掃除は窓を閉めたままで
え~って思われるでしょ?
ホコリがたつので窓を開けて換気を良くした方がいいって教えられてきませんでしたか?
それは掃除が済んだ後のことなんです。
ホコリはすごく軽いモノなのでちょっとした風や空気の動きですぐに舞い上がってしまいます。
だから窓を開けたままで掃き掃除をすると余計に部屋をホコリだらけにしてしまうのです。
正しくは、
- 窓を閉めたまま
- エアコンやファンヒーターなども停めて
- 掃除機ではなくて
- ペーパーモップで掃き掃除をする方がいいのです。
※掃除機は排気でホコリを舞い上げてしまい
ますので、最初はペーパーモップがオススメです。
-
掃除は夜の方がベスト
たった1gのホコリの中に約2000匹のダニがいると言われています。
このダニは夜行性なんです。
だから畳や毛の深いジュータンなどでは、昼間は下の方にもぐっています。
いくら掃除機でも深くもぐったダニには効き目が少ないのです。
だから掃除は夜にした方が効果的なんです。
でも、夜に掃除をすると騒音や時間がないと言われます。
そんな時は、昼間でもカーテンを閉めて照明も暗くします。
30分ほど待てばダニは活動し始めますから一網打尽ってわけです。
-
ペーパーモップは両面使える

意外に知らない人が多いのですが、ほとんどのメーカーのペーパーはリバーシブルなんです。
ちゃんと包装紙の表示に記載していますが読まない人が多いのです(笑)
汚れたら裏返しにすれば倍使えます。
ただ汚れた面を裏返しにするとモップの面が汚れるのでは?と思う人もいます。
そんな方は、ペーパーとモップの面の間にティッシュを1枚はさめば解決です。
-
浴槽はスポンジでこすり洗いはダメ!

殆どの人は洗剤を浴槽に吹き付けて、スポンジなどでこすり洗いをしてるでしょ?
それって、あまり良くないんです。
こすり洗いをすることは浴槽に傷をつけてしまいます。
その傷に人の垢や水垢を入り込んで余計に頑固な汚れになったり、カビなどの原因にもなります。
それと、スポンジで洗う時に頭が浴槽の中に入ったり近くなっていますよね。
中には浴槽の中に入って洗う人もいます。
この状態はかなり洗剤を吸い込んでいる格好になっていますよね。
健康にも良くありません。
正しくは、
- 洗剤や重曹水などを浴槽に噴きつけたら、
- 10分以上そのまま放置して、
- その後、少し熱めのシャワーですすぐです。
どうしても頑固な汚れの時だけスポンジで撫でるように優しく洗ってください。
換気が足らない!1に換気、2に換気です。

とにかく今の日本の家は「換気」が足らなすぎるのが実態です。
そのことから様々な問題を引き起こしています。
夏は湿度が高くて、冬は空気が乾燥していると言いますが、一概にはそうとも言えないんです。
確かに冬の外気は乾燥していますが、今の日本の家の中は冬でも湿度が高いんです。
窓がサッシになったり、外壁もしっかりしていますので隙間風がありませんよね。
そうした密閉された家の中で料理をしたり、特に鍋が増えてきますし、加湿器を使っていますので結構湿度が高いんです。
確かに、女性のお肌のためにとか、インフルエンザなどの予防のためには加湿をしていた方がいいです。
でも、これが冬でもカビや魔物(ゴキブリ、ダニなど)を増やしてしまう原因にもなっています。
とにかく、今の日本人は換気が足りないのが実態です。
窓を開けたり、換気扇をまわして時々は換気をぜひして下さい。
風邪やインフルエンザ予防のために加湿をするだけで換気をしないと、家の中の空気が循環しなくて滞ります。
すると、逆に菌をもらいやすくなります。
扇風機を使った換気の方法

私は冬でも扇風機を1台は出しっぱです。
たぶん、整理収納アドバイザーなのに、ダラシナイなって思われてるかも ^ ^
押入れ、クローゼット、下駄箱など湿気が溜まりやすい場所に扇風機が便利です。
扉を開けっ放しにして、扇風機を首振りにしタイマーを1時間くらいセットして中に風を送り込んでください。
これだけでもかなり湿気は飛びますので除湿剤は要らなくなります。
時々はタンスの引き出しや衣装ケースも開けて換気をした方がいいですね。
折角、洗濯やクリーニングに出して収納しても、密閉したままなのでカビが生えてしまうこともあります。
キッチンの換気扇のスイッチを入れるタイミングの間違い

換気扇の使い方も多くの人が間違っていますね。
コンロに火をつけるタイミングで換気扇のスイッチを入れてるでしょ?
もうそれでは手遅れなんです。

少なくとも火をつける5分前に換気扇を回さないと空気の流れができていないので、充分に換気できないんです。
だから、さぁ料理を作ろうかとキッチンに立った時が換気扇のスイッチのタイミングです。
それと、料理が終わったらすぐにスイッチをオフにするのも早すぎます。
調理が終わっても最低5分はまだスイッチを切らないでください。
油料理じゃないからとか、お湯を沸かすだけだからとか、換気扇がうるさいからって、換気扇のスイッチを弱や中にするのもダメです。
とにかく、換気扇は常に強がオススメです。
お風呂の換気扇は朝までつけっ放しでカビ知らず
お風呂も同じで、換気の時間が多くの人は足りません。
だからカビが生えやすくなるんです。
お風呂の換気扇は家族が入り終わったら、朝までつけっ放しがいいです。
とにかく、カラッカラッにしておけばカビは繁殖しませんから。
換気扇は24時間回しっぱなしでも電気代は安い。
私のオススメはキッチンかお風呂の換気扇を24時間回しっぱなしでもいいと思います。
その時は弱か中でいいです。
マンションは特に密閉された空間なので、特に空気が淀んでいます。
どこか1ヶ所だけでも換気扇を回しておけば家じゅうの空気は流れができますので、菌の蔓延やカビ、防虫対策になります。
片づけの習慣はルーティンで身につければ簡単です。

あなたは夏休みの宿題は早く済ませておくタイプでした?
それともギリギリ派でした?
ギリギリ派の子供は毎年ギリギリなんですよね。
なぜそうなるかって言うと、ギリギリでも何とかなった、間に合ったという経験がそうしてしまうらしいです。
私は「あとかたづけ」は「今すぐ片づけ」とお話ししています。
「あとで」とか「また今度」、「いつか」と言って先送りにしてしまうのは「あとかたづけ」ではないんです。
散らかってきたから片づけるではなくて、散らからないように片づけておく。
汚れがひどくなってきたから掃除や洗濯をするではないんですね。
だけど面倒くさい!って思ってしまいます。
じゃあ、ご飯を食べるのは面倒くさいですか?
服を着るのは面倒くさいですか?
それは面倒くさくはないはずです。
そこにはある種の「楽しさ」や「楽しみ」が待っているからです。
一方、食べた後の食器を洗って片づけるのは面倒くさい。
脱いだ服をたたんだりハンガーに掛けて片づけるのは面倒くさい。
もうそこには「楽しさ」や「楽しみ」を感じられないからです。
だけど、ご飯を食べたり、服を着るのと同じくらい、「片づけ」や「掃除」は絶対にしなくてはいけないことなんです。
人がモノを持ち、生活している以上絶対にしなくてはいけないことなんです。
自分のハードルを上げすぎないこと!
そういった面倒くさいことを習慣にしていく方法は、まずはハードルを上げすぎないことです。
毎日、家の中を掃除してくださいって言ったらどう思いますか?
じゃあ、毎日浴室全部を掃除してくださいだったら?
それでも嫌かもしれませんね。
じゃあ、毎日お風呂から上がる時にお湯のシャワーを壁と床にかけてくださいって言ったら?
じゃあ、鏡だけでも毎日拭いてくださいだったら?
だったら少しできそうな気がしませんか?
とにかく、無理なことを自分に押し付けないことが大事なんです。
ルーティンで片づけや掃除の習慣や癖を身につける
さらに、習慣化させる効果的な方法は五郎丸選手で有名になったルーティンです。

イチロー選手もやってるし、オリンピックで金メダルをとった内村選手も跳馬の時にやってましたね。
ルーティンって、何かをする前とか後に必ず行う行動です。
これを習慣を身につけていく方法として活用すればいいわけです。
毎日必ずすることってあるでしょ?
朝ごはんや夕食を食べるとか、お風呂に入るとか。
片づけや掃除をそうした必ずすることの前後にくっつけてみるんです。
例えば、私の夏休みは朝のラジオ体操に行って帰ると、そのまま宿題を済ませて、10時になったら遊びに行ってました。
カギや携帯をいつも捜している人は置き場所を決めて、家に帰ったらすぐにそこへ置くと言うルーティンにしてみてください。
これを意識して3日間続けてみると、人の意識は習慣を身につけていくのが分かります。
さらにそれを繰り返していくと、習慣が「癖」になっていくわけです。
癖になったらもう簡単には忘れません。
だけど、私もギリギリ派だったのは、読書感想文!
だから今でも文章を書くのが苦手です ^ ^
襟・袖の汚れを簡単に落とす裏ワザと汚れにくくする楽ワザ

カッターシャツやブラウスなどの襟や袖汚れが気になると思います。
あの黄ばみや黒ずみは人の皮脂や垢、ホコリなどが混じったものです。
これを放置しておくと繊維の中までしみ込んでいって頑固な汚れになるわけです。

ただ、人の皮脂は本当はそんなに怖くないんです。
大事なことは汚れを放置しておかず、できるだけ早く処置しておくことです。
脱いだらすぐに湯洗いするだけでOK!

皆さんにオススメなのが、湯洗いです。
帰宅して服を脱いだらすぐに洗面所に行って熱めのお湯(50~60℃)を、襟や袖にかけてください。
それだけでも、かなり汚れが落ちていきます。

もっと効果的なのは、さらに固形石鹸や食器用洗剤をつけてモミ洗いしておいておくだけ。
あとは他のモノと洗濯すればいいです。
白物の服はすぐに汚れるからと言われる人もいますが、それは間違っています。
すぐに汚れるのは白だろうが色物だろうが同じです。
白物は汚れやすいのではなくて、汚れが目立ちやすいだけです。
だから、白物だろうが色物だろうが、早めにひと手間の処置をしておいたり、すぐに洗濯しなければいけないんです。
簡単なひと手間で襟・袖が汚れにくくなる方法
≪汚れたら洗う≫は当然ですが、汚れにくくまたは汚れても落ちやすいように工夫しておくとラクですよね。
特に襟や袖の皮脂汚れがつきにくく、または落ちやすいようにしておく方法があります。
①のりづけしておく
洗濯のすすぎの時に洗濯のりを入れておく。
または、襟と袖だけでもスプレーのりをしてアイロンしておく。
それも面倒だったら、着る時に襟袖の内側だけにスプレーのりを噴霧しておく。
つまり、のりのコーティングをしておけば汚れが直接繊維に付着するのを防ぐことができます。
汚れはのりの上に付いている状態ですから、洗う時にのりが落ちると同時に汚れも落ちるという仕組みです。
②ベビーパウダーを少量つけておく
着る前に襟や袖にベビパウダーを付けておきましょう。
ペビーパウダーの粉が汗や皮脂を吸着してくれます。
そのお陰で繊維の奥まで汚れが浸透しにくくなります。
※付けすぎると舞妓さんになるのでご注意を!(笑)
③重曹水、セスキ炭酸水を噴霧しておく
重曹やセスキ炭酸は油汚れの分解力が高いです。
油に強いということは皮脂にも同じ効果があります。
500mlの水に大さじ1~2杯の重曹かセスキ炭酸を溶かし着る前にスプレーで襟袖に噴霧しておくといいでしょう。
④クレンジングオイルを薄くぬっておく
女性が化粧落としに使うクレンジングオイルです。
化粧品は強力な油です。
油を落とす効果のあるクレンジングオイルを着る前に襟袖に薄く塗っておくだけで汚れが繊維の奥に浸透するのをかなり防ぐことができます。

5月30日はゴミゼロの日|整理はゴミを捨てるから始めましょう!

皆さんは、5月3日と5月30日は何の日かご存知ですか?
答えは、「ゴミの日」と「ゴミゼロの日」です。
ゴロ合わせだと思いますが、5月にはゴミに関する日が2回もあるんです。
ゴミってどういう意味ですか?|ゴミの定義
実は辞書にはこう書いています。
“おいおい、俺のことか?!”って思われた方もいるかもしれませんが 笑
では、押入れ等に押し込まれたミシンやホームベーカリー、使っていないシャモジ、包丁などのキッチン用品。
引出しの中の細々とした小物たち、随分着ていない服、バッグ、靴、などは何でしょうか?
このゴミの定義で言えば、全部ゴミです。
まぁでも、これらをすぐに捨てましょうは難しいと思います。
でも、少なくとも明らかにゴミになっているモノから処分されてはいかがでしょうか?
それだけでも、かなりモノは減るし、綺麗になっていくはずです。
日本はゴミ大国|焼却炉の数は世界一!

このゴミ問題は本当に今深刻です。
日本にゴミ焼却炉が約1300あります。
これは世界ダントツ1位です。
第2位はアメリカですが、この1300という数は、日本の3倍の人口、国土も日本より広いアメリカの約4倍なんです。

国民一人あたりのゴミ焼却量も、ダントツ世界1位です。
経済大国と言われている一方で、ゴミ大国でもあるわけです。
COP21という世界会議で地球温暖化について話し合いが行われました。
1997年には京都議定書と言われる日本でも行われました。
世界の首脳クラスの人や科学者たちが集まりどうしようかと話し合っているわけですが、地球環境は全然解決できていません。
なぜでしょう?
一番の問題は、そうした偉い人が何とかしてくれるとか、科学の力で解決できるだろうと、私たち一人一人の意識や行動が改善されていないからだと思います。
例えば、エコバッグ、マイ箸運動、ペーパーレス運動、過剰包装をやめるなどはどこへ行ってしまったのでしょうか?
いっときのブームで終わっただけではないでしょうか?
買い物にエコバッグを持っていっている人は僅かです。
マイ箸で食べている人はほとんど見ません。
ビジネスや政治の世界ではペーパーレスどころか大量の紙を使っています。
日本ではまだ食べられる食料を1年間で約2000万トンも捨てています。
その処分に2兆円を使っていると言われています。
こうして日本人はゴミ袋が有料化になってもゴミを増やし続けています。
だから焼却炉や埋立地もたくさん作ってきたわけです。
こんなゴミだらけの日本や世界を子供たちに委ねるのはあまりにも残酷ですよね。
もう一度、ゴミゼロの日を機に自分を見つめなおしてみることが大切だと感じます。
旅行や出張のバッグの上手な荷造り・パッキングとは

今日は4月21日。
もうすぐゴールデンウィークですね。
GW以外でも旅行や出張に行かれる機会がありますね。
そんな時にお役にたてるバッグの収納のワンアドバイスをさせていただきます。
つまり荷造りです。最近はパッキングとも言います。
トランクやキャリーバッグを買うのはモッタイナイかも
まず最初に整理ist としての忠告は、今後頻繁に使うかどうかも分からないのに、いきなり大きなトランクやキャリーバッグを買わない事ですね。
年に数回しか使わないモノにお金を使うのはモッタイナイです。
レンタルで借りたり、友達などから借りてもいいわけですから。
お金もモッタイナイですが、大きなバッグは家の中で結構収納スペースをとってしまいますからね。
スーツケースは借りるのが絶対にオススメです!
↓ ↓ ↓ ↓
要らないモノは持って行かないことです。

特に衣類や靴などですね。
日帰りなら必要ないと思いますが、宿泊する場合は何着か持っていくと思います。
衣類はバッグの中で一番スペースを取るものですから、できるだけコンパクトに絞り込んだ方がいいです。
パンツ(ズボン)やスカートは1着にして、トップスを日数分持って行くみたいな感じです。
とにかく、これも着るかも、これも着るかもってのは危険です。
荷造りする前に、衣類・アクセサリー・靴をまずはコーディネイトして、それだけを持って行くようにしてみてください。
荷造りの上手な方法やコツのポイント
- 小物は小分けしておく
化粧品、スマホの充電器など小物の荷造りで私が活用しているのが、チャック付ビニール袋(ジップロック)です。
巾着やポーチもいいんですが、透明な袋の方が分かりやすくていいです。
特に海外の税関で中身が見えない袋だと見せないさい!ってことにもなることがありますから。
- 薬とボールペンを忘れずに
結構忘れがちなのが、薬と筆記用具です。
いつも服用している人でも旅行となると忘れる人が多いです。
胃薬、酔い止め、絆創膏は持って行った方がいいかも。
国内でもいざって時にお店がなかったりします。
また酔い止めは頭痛薬としても使えますよ。
- 洗濯用ネットの活用

1泊なら洗濯用ネットに下着や靴下を入れて持っていけば、汚れたものはそれに入れて持って帰ればそのまま洗濯できます。
2泊以上でしたら、洗濯用ネットの大きめを1枚余分に持って行けばいいです。
- シャワーキャップの活用

多くのホテルにはシャワーキャップが置いてあります。
それに着替えた下着や靴下を入れて帰ってもいいですね。

靴やビーチサンダルなどを入れれば、砂や土がバッグの中を汚すのを防いでくれます。
- 巻きずしパッキング

周りに丸めた衣類やタオルなどを収めて、真ん中に小物や壊れやすいモノを入れてください。
特に海外だとバッグが乱暴に扱われることがありますから、この方法がオススメです。
- ミルフィーユパッキング
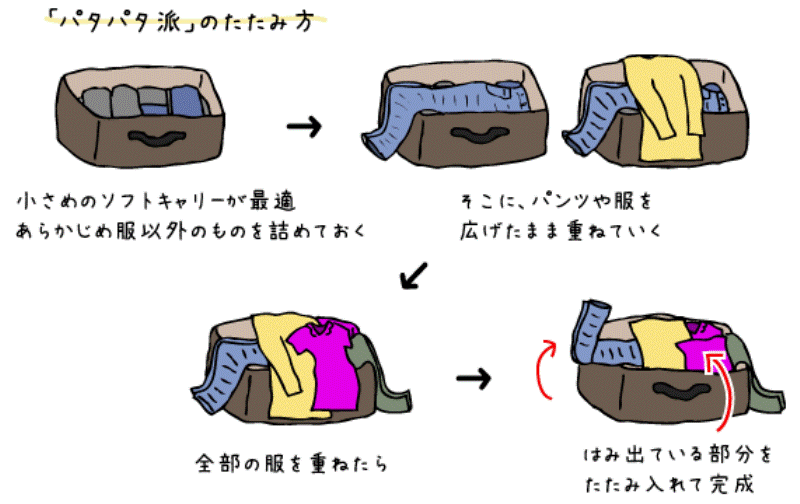
服を丸めるのが嫌な人はこの方法がオススメです。
パンツ、スカート、ワンピース、ジャケット等畳まないで服をそのままキャリーバッグに敷いていきます。
バッグからはみ出たままでいいですので、1枚1枚を十文字に次から次へと敷き重ねていきます。
まさに服のミルフィーユです。
敷き終わったら、真ん中に小物などを入れてバッグからはみ出ている部分を中に畳んでいきます。
こうすると、シワも付きにくく、壊れ物も真ん中で守られています。
- 薄手のダウンかカーディガンを持って行く
たとえハワイであっても薄手の防寒着は持って行った方がいいです。
長雨になったり、朝晩は冷え込んだりしますから。
それと、こうした衣類はバッグの中でクッション代わりになります。
- 旅の下着は、はき捨て
「旅の恥はかき捨て」ではなく、「旅の下着ははき捨て」です。
お叱りを受けるかもしれませんが、下着や靴下など、もうそろそろ処分しようかなと思うものをはいて行きます。
旅先でお別れして帰る方法は、旅慣れている人がよくやっています。
その分帰りの荷物が減らせますので。
- 8割パッキング
行く時にギューギュー詰めで行くと、帰る時の荷造りはバッグが閉まらなくなります。
お土産も買ったりしますからね。
2割程度の余裕のある荷造りをしておいてください。
- 安易に備品を持って帰らない
ホテルの石鹸やクシとかを持って帰る人がいます。
だけど必ずって言っていいほど自宅のゴミを増やしてしまうはめになっています。
持って帰らなきゃ損とかモッタイナイと考えてはいけません。
そのまま置いておけばリユースやリサイクルになってエコになると考えてください。
借りれる物は借りるのが一番です!
↓ ↓ ↓ ↓
ブログ著者 ロハスカタス 整理ist佐藤亮介のセミナー・講座・サポートのご案内
下記のページをご参照ください。
モノ屋敷だった私が「スッキリ・キレイ整活」を実現できたノウハウを無料で購読できます。捨てられない人、散らかし癖のある人に必ずお役にたてる私からの毎朝のメッセージです。