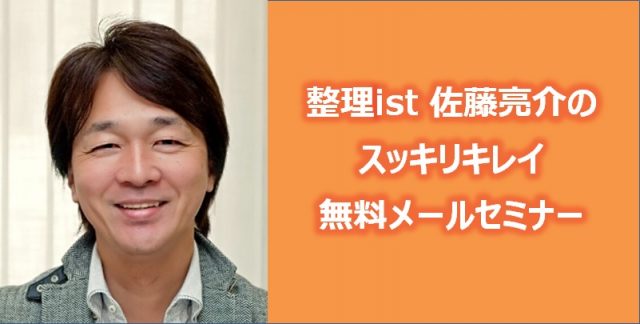捜し物をしない収納・片づけが簡単収納で時間とストレスを解決しましょう!

目次
捜し物大国?日本!あなたは毎日捜し物をしていませんか?
早く「収納」についての話を聞きたいところでしょう。
だけど私は「収納術」や「収納グッズ」の紹介がメインではないので、まずは「序文」をお話させてください。
当然のことですが、私たちはモノを捜すために生まれてきたわけでも、モノを捜すために今日を生きているわけでもありません。
以前、Zippoというオイルライターの会社が世界数か国の国民を対象に「モノを捜している時間」を調査したことがあります。
その結果、日本人は一生のうち平均で75,322分間、つまり52日間をモノを捜すために時間を費やしていることがわかりました。
さぁ、あなたはいかがですか?
毎日、何かしら捜し物をしていませんか?
「捜す」と「探す」の違いって知っていますか?
私たちは「さがす」を文字にする時に2通りの漢字がありますよね。
「さがす」で変換すると「捜す」と「探す」が出てきます。
これ、ちゃんと使い分けていますか?
まぁ、どっちでも通じるっちゃ通じるわけですけどね(笑)
正確には同じ「さがす」でも、「さがす対象」によって使う漢字は変わってきます。
旺文社国語辞典 [第九版]によると、
「捜す」は、見えなくなったものをさがしだす意で、「犯人を捜す」「落とし物を捜す」「迷子を捜す」などと使われる。
「探す」は、ほしいものを見つけようとする、きわめる意で、「宝物を探す」「職を探す」「住まいを探す」などと使われる。
つまり、私たちの日常で「モノをさがす」行為は「捜す」が正しいということになります。
だけど、中には押入れの中や引出しの中を「探検する」という「探す」になっている人も少なくないのかもしれませんね(笑)
バッグの中、財布の中を捜す・発掘している人
例えば、こういう人はいませんか?
あなたはどうですか?
- バッグの中から財布がなかなか見つからずバタバタしている人
- ポイントカードやクーポン券を“あれ?どこだっけ?”って捜している人
- 俺のスマホは?“悪いけどちょっと鳴らしてくれない?”
- おかしいな~ カギはバッグの中に入れてたんだけどなぁ
こういう人いますよね。
私はそのシーンだけで、その人のバッグや財布の中が見えてきます ^^
更には、その人の家の中が見えてきますと言っても過言ではありません。
モノを捜す時間は一番モッタイナイことです!Time is Life(タイム イズ ライフ)
Time is Money(時は金なり)という言葉があります。
だけど、私はさらにこう言います。
Time is Life
「時は命なり」です。
私たち全ての人間に平等に与えられているのが「命」と「時間」です。
つまり、「時間」は「命」と同じってことです。
前述しましたように、私たちは少なくともモノを捜すために生まれ、生きているわけではありません。
モノを捜す時間は自分の「命」を削っている行為だと思っています。
日本人がそもそも考え、教えとしてきた「モッタイナイ」とは「物体ない」が語源です。
つまり、そこには「時間」も含まれるということなのでしょうね。
捜す時間が会社の経費増や利益減に影響している!
私は全国のオフィスや店舗の環境改善コンサルをしています。
最初に伺った時に私が行うのは全社員アンケートです。
その中の1項目に
「あなたは仕事時間中にモノを捜している時間は何分くらいありますか?」と尋ねています。
ある社員数約100人規模の会社でこのアンケートを実施し、集計を行いました。
その結果、一人当たり35分捜し物をしているという実態が見えてきました。
その結果を社長をはじめ皆さんに報告すると、シラ~ってしているんです。
35分が長いのか短いのか、ピンときていないわけです。
中には、“ほー、わが社は優秀だな!”って言う役員さん。
“まぁ、そんなもんだろ”って言う人も。
だいたいどこの会社でも似た反応なので想定内でした。
そこで準備していた次の発表をしたわけです。
“この会社のトップから新入社員までの平均時間給から、この35分を計算してみました。”
“年間稼働日数で計算してみると、2,640万円になりました!”
“さぁ、これでも優秀ですか? 「そんなもんだろ」で済みますか?”
すると、“えー、そんな金額になるのか!”
“全然たかが30分じゃないじゃん!”という声が聞こえてきます。
社長や役員の方が一番青ざめていました ^^
見方を変えれば、この会社は年間2,640万円を「捜す」経費に使っているということになります。
利益どころかマイナス経費です。
お金をドブに捨ててるというのは言いすぎでしょうか?
これはご家庭でも同じです。
「捜す」時間は何も生みません。
逆に、イライラ感やストレスを生みます。
こうした視点からも改めて「モノを捜す時間」について考えていただきたいです。
では、「モノを捜さない」収納や仕組みはどのように作ればいいのか、
いよいよ本題に入っていきます。
定位置管理|モノの指定席・モノの住所を決める
まず私が一番にオススメしたいのが、モノの「定位置管理」です。
これは整理収納アドバイザー講座の中で使われている専門用語です。
分かりやすく言い換えますと、「モノの指定席をつくりましょう!」ということになります。
もっと分かりやすくするために、私は
≪モノの住所を決めましょう!≫と言っています。
私にも、あなたにも家の住所がありますよね。
住所があるから郵便物や荷物が届きますよね。
いくら私が酔っぱらってても住所をタクシーの運転手さんに言えば連れて帰ってくれますよね(笑)
同じようにモノにも住所を決めなければ、いくら“使ったら元に戻してよ!”って怒鳴っても、モノが帰る場所が決まっていなければ戻ってこないのです。
モノが自分で元に戻ってくれるのはお掃除ロボットだけです(笑)
モノ屋敷の住人だった私だけどモノを捜したことがありません。
私は拙著「一生つかえる整理力が3週間で身につく本(明日香出版)」にも、自分の過去をカミングアウトしています。
そのため私がモノ屋敷の住人だった話は多くの人が知っています。
ただモノ屋敷だった私ですが自分の家でモノを捜すことをほとんどしたことがありません。
モノ屋敷なのになぜ?って思いませんか?
それは私は唯一、この定位置管理だけはできていたからです。
幼少期に母親から「片づけ」を厳しくしつけられていたので、自分が使ったモノはすぐに元の戻す「片づけ」の癖が身についているのです。
そして、そのために必要なモノの住所が決まっているからなんです。
もしも、あなたがモノが捨てられない人でしたら、あなたには特にこの「定位置管理」というモノの住所を決めることから始めてみることをおススメします。
モノの住所が決まれば、元に戻す習慣が身につきやすくなります。
そうすると、いつしか最近モノをあまり捜さなくなった自分に気がつくはずです。
いきなりモノを減らすことだけが入口ではありません。
モノを捜すストレスから解放されるだけでも、必ずあなたの暮らしは快適になるわけですからね。
テレビのリモコンはテレビ台の上を定位置(住所)にしました!という事例

あるお宅で〝テレビのリモコンがいつも行方不明になって捜索願を出してます^^〝って相談されました。
〝それでは、とりあえずリモコンの住所を決めましょうね。どこにしたいですか?〝 とお尋ねしました。
すると、奥様は〝じゃあ、テレビ台にしてみます。〝とおっしゃいました。
さぁ、みなさんいかがですか?
一緒に考えてみましょう。
「テレビのリモコンの住所をテレビ台にする」はいかがでしょうか?
答えは ▲なんです。
完全に間違いではありませんが、これでは不十分なんです。
解説しますと、私はモノの「定位置管理」とは、モノの「住所」を決めることだと言いましたね。
つまり「リモコンはテレビ台の上」では、まだ住所になっていないわけです。
これではまだよく分かりませんか?
皆さん、住所ってなんでしょうか?
例えば私のオフィスの住所は、岡山県久米郡久米南町神目中242番地です。
つまり住所とは番地までが住所です。
「リモコンはテレビ台の上」というのは住所ではないわけです。
下の絵を見てください。
テレビとテレビ台を真上から見ています。

「リモコンはテレビ台の上」というのは、オレンジ色の部分全部になりますよね。
これは「定位置管理」、モノの住所決めにはなっていないのです。

上の絵のように、例えば黄色の円の部分がリモコンの住所です。
※黄色の円が左端でも真ん中でも構いません。
モノの住所は具体的にココという番地まで決めた住所にしなければいけないのです。
一方で、この問題を出した時に受講者の方からこのような答えが返ってくることもあります。
“テレビ台の上は良くないと思います。”
私がそれはなぜですか?とお尋ねすると、
“テレビ台の上だと、いちいちチャンネルを変えるたびに取りに行かなくてはいけないから”とお答えになりました。
確かにそれも納得できます。
ただ、「片づけ」というのは、あくまでも≪使い終わったら元に戻す≫なんですね。
ですから、テレビを見ている最中はまだ使い終わっていないので、その間は食卓の上に置いてても構わないのです。
「テレビを観終わって電源を切る」、これが使い終わった時ですから、その時はテレビ台の上の住所に戻すで構わないのです。
電話の子機の住所はキッチンカウンターの充電器としています。
でも昼間はよく使うので食卓テーブルの上にあっても構いません。
ただし、一日の終わりなどにはキチンと充電器という住所に戻しましょうとなります。
「定位置管理」、モノの住所について理解していただけたでしょうか?
さぁ、始めてください。
あなたのカギの住所は決まっていますか?
“はい、玄関です”
これでは不十分です。
まだ岡山市までしか決まっていませんね ^^
帰宅した時のスマホの住所は?
バッグの住所は?
バッグの中の財布の住所は?
モノの住所が決まってくると片づけの習慣も身につきやすくなります。
無理をせず、いつもよく捜しているものから住所を決めて試してみてください。
★注意★
モノの住所は一度決めたらもう変えられないというのは違います。
その住所が適していなかったり、なんだか不便だったり、その住所では元に戻す習慣が身につかない。
そんな時は何でも新しい住所の新居に引っ越しても構いません!
定位置(指定席)管理、モノの住所を決める収納事例
幼稚園児でも片づけしやすい簡単・分かりやすい方法

岡山のある幼稚園で見つけた椅子の収納です。
床に白いテープで囲っていますよね。
子供たちはこの線の枠の中に椅子を片づけるのかって分かりやすいですよね。
さらに、↓ このラベリングに注目してください。

先生が口で、“椅子は5つ重ねて置きましょう!”と言うよりも、この方が一目瞭然ですよね。
こうした仕組みを上手に作ることで、私の言う自分以外の人への「おもいやり収納」が完成するのです。
ランドセルの定位置(指定席)を決めて子供もママも楽になりました。

このご家庭では、お兄ちゃんも妹さんも学校から帰宅すると、リビングのこの台の上にランドセルを置きます。
二人のランドセルの定位置(住所)はココなんです。
このお宅では「ダイニング・スタディ」形式をとっているので、宿題は子供部屋ではなく食卓なんです。
だから、ランドセルの定位置(住所)はリビングでいいわけです。
ランドセルのフタがこっち向きに置いているのもポイントですね。
フタがこっち向きに開け閉めできた方が教科書やノートを取り出しやすいですよね。
もうひとつ、大事なポイントがこのお宅ではありました。
それは、このランドセルの定位置(住所)は、ママが勝手に決めたのではなく、わが子の希望も聞いてお子さんと一緒に決めたことが素晴らしいのです。
親が勝手に決めると、子供は“ママが勝手に決めたんだし”って言うことをきいてくれません。
是非、子供と同じ目線で、同じ扱いをしてあげてください。
薬箱、薬置場がキッチンの食器棚を定位置にした理由

皆さんのお宅には薬箱か薬置場はありますか?
薬は絆創膏や頭痛薬、体温計程度でも一か所にまとめておくことを是非なさってください。
普段使う頻度は少ないかもしれませんが、薬っていざっていう時、急に必要になるものです。
そのために家族が誰でも分かりやすい収納を心掛けておくことが大事です。
因みに私の家での薬箱の収納場所はキッチンの食器棚の中なんです。
“えっ、なぜそんな場所に?”って思われた方もいらっしゃるでしょうね。
理由は次の2点です。
- 絆創膏の使用頻度が一番多いから(包丁やハサミで指を切るとか)
- キッチンで火傷をすることもあるから
- 頭痛薬などの錠剤や粉薬をのむ時には必ず水が必要だから
指を切って血が出る、火傷をしたという緊急事態の時にすぐに手が届く場所の方が処置は早いですよね。
皆さんのお宅の薬置場をこうした観点からもう一度見直してみてはいかがでしょうか?
モノの定位置(住所)はココじゃなきゃダメ!というルールはありません。
人や家庭で違ってても構いませんっていうか、当たり前なんです。
決して、テレビや雑誌で紹介されていることだけが答えだとは絶対に思わないでくださいね。
小物(文具、乾電池など)は誰でも分かりやすい収納に

捜し物のトップ3に入るのが小物です。
“爪切りはどこ?” “ハサミは?” “朱肉ってどこにあるの?”
⇒ “もう、いつものとこにあるでしょ!”
こうした会話が頻繁にあるご家庭では小物の定位置(住所)が決まっていないか、家族に認知されていない収納になっているのかもしれません。
“冷蔵庫はどこだっけ?” “テレビってどこに置いたの?”そんなことは言わないはずですよね(笑)。
つまり、小物ほど定位置(住所)を決めておく必要があるのです。
そして、定位置が決まりましたら、ラベリングと言って、中に入っているモノを見出し的に書いて貼っておくと便利です。
こうした収納の仕組みこそが、私の提唱している「おもいやり収納」ということです。
ラベリングの効果は
- どこに何があるのか一目瞭然
- 使い終わったあとの片づけの場所も分かりやすい
- 違うものが混ざりにくい(靴下って書いた引出しにパンツを入れる人はいません)
このように定位置管理とラベリングを併用すると、速攻で効果が目に見えて実感できます
ので是非すぐにお試しください。
子供もラベリングでおもちゃの片づけができるようになりました。


ラベリングは必ずしも文字じゃなくても構いません。
この事例は、あるご家庭で作った子供向けのおもちゃの収納の仕組みです。
子供が自分でお片付けができるようにとママが希望されていましたので、私はそこのお子様と一緒に遊びながら作っていきました。
“おじさんと一緒に駐車場をつくろうか?”
“ぷーさんって夜はどこで寝てるの? 寝るとこ作ってあげようよ”
子供の意見も聞いて定位置を決めていきます。
そして、ラベリングですが、まだ文字が十分に読めません。
だから写真にしました。
※字が読める子でも文字よりも写真やイラストの方が分かりやすいし、喜んでくれます。
最後に私は子供たちにお願いをしました。
(決して強制ではなくお願いの姿勢です)
“ダンプやパトカーのお仕事が終わったら車はここにとめてくれるかな?”
“ぷーさんは夜はここで眠らせてあげてね”
こんな感じで子供と一緒につくっていくのです。
子供たちは楽しそうに手伝ってくれますし、“うん、わかった”って片づけてくれます。
靴を脱ぎっぱなしにしていた子供が下駄箱に片づけるようになった仕組み

このお宅のお手伝いに行った時に、ママが“うちの兄弟は外から帰ると靴を脱ぎっぱなしにして片づけないんです”と嘆いていらっしゃいました。
そこで、私は男の子二人を呼んで“おじさんと一緒にシール遊びをしようよ”と声を掛けました。
お兄ちゃんは青のシールを選びました。
弟は緑のシールを選びました。
“じゃあ、自分の靴のかかとにシールを貼ってみよう!”
“次は、それぞれのシールを下駄箱の棚に貼っていこう!”
“よしできたね。手伝ってくれてありがとう。助かったよ。”
“お願いがあるんだけど聞いてくれる?”
“今日から青の靴は青のシールのとこに、緑の靴は緑のシールのとこに、靴を脱いだら置いてくれたら嬉しんだけどな”
その日以降、この兄弟は靴を玄関に脱ぎっぱなしにすることはなくなったそうです。
子どもには怒ったり、〝なぜできないの!〝って否定したり、強要しても無駄なんです。
あなただって、誰かに同じように言われたら嫌でしょ?
子どもだって同じです。
「片づけ」を遊びやゲーム感覚で一緒に作ってみてあげてくださいね。
収納はジコチュウではなく、「おもいやり収納」で作ってください。
収納は自分だけ決めて作ってしまうと他の人が付いてきてくれません。
他の人のことも考え、相手が子供なら同じ目線で考えてください。
意見や希望をちゃんと聴いてあげてください。
そして、一緒に作ってください。
相手が子供なら一緒に遊ぶ感覚でやってください。
あなたが勝手に決めて作るのではなく、「おもいやり収納」を絶対に忘れないでくださいね。
ブログ著者 ロハスカタス 整理ist佐藤亮介のセミナー・講座・サポートのご案内
下記のページをご参照ください。
モノ屋敷だった私が「スッキリ・キレイ整活」を実現できたノウハウを無料で購読できます。捨てられない人、散らかし癖のある人に必ずお役にたてる私からの毎朝のメッセージです。