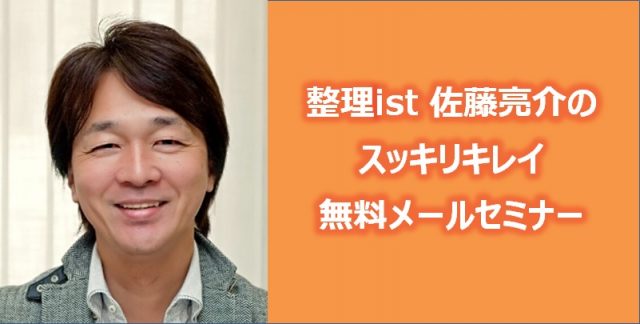子供の片づけ上手と学力の相関関係|宿題のギリギリ派、何とかなる派、早めに派、コツコツ派

あなたは子供の頃に、夏休みの宿題や毎日の宿題は、「早め派」でしたか? それとも「ギリギリ派」でしたか?
あなたのお子さんは、いかがですか?
「ギリギリ派」の人は、おそらく毎年「ギリギリ」だったのではないでしょうか?
あなたのお子さんはいかがですか?
実は、この「ギリギリ」が、片づけが苦手な子供や大人にしてしまうってご存知でしょうか?
夏休みや冬休みだけでなく、毎日の宿題の終わらせ方が、片づけができない人や、物をなくしがちな人をつくってしまう原因になっているのです。
お子様をお持ちの方には特に読んでいただきたいお話です。
最後までお付き合いください。
スッキリ・キレイ整活3S(整理・掃除・洗濯)講師の整理ist 佐藤亮介
目次
子供の約60%は宿題は「ギリギリ派」という調査結果

ある子ども向け教材会社が調査した結果です。
「計画的に毎日少しずつ片づける」が、約40%に対して、「全部終わらない」とか「手を借りて」「慌てて」が約60%でした。
あなたは子供の時にどれでしたか?
あなたのお子さんはどれでしょう?
宿題ギリギリ派にしてしまう原因は?

毎年、夏休みや冬休みの宿題が、または毎日の宿題がギリギリになってしまう原因は・・・・・・
「なんとかなった」です!
もうすぐ新学期、もう寝る時間、だけど子供がまだ宿題が終わっていない。
すると、親は見るに見かねて手伝ってしまします。
漢字ドリル、算数ドリルを親が我慢できずに答えを教えてしまうパターン。
絵や工作、読書感想文、自由研究、先生たちは「どう見ても、これ本当に子どもの作品?」って思えることがあるそうです。
こうして親が手伝うことで、確かに宿題はでき、無事に子供は学校で怒られなくてすみます。
だけど、子どもからすると、いざとなれば「まぁ、なんとかなるものだ!」という意識が定着してしまうのです。
これが脳科学で言う「脳の甘えの構造」です。
人は誰しも楽をしたいものです。
できることなら、辛い経験はしたくないと思います。
「なんとかなった」という経験が、脳を甘えさせ、横着の習慣や癖をつけてしまうのです。
これは、1度経験してしまうと脳は快感になりますので、毎年や毎日の宿題は常に「ギリギリ」です。
忘れ物や失くし物が多い人は親が用意や片づけをしていたのでは?

こうした脳の甘えの構造は、宿題だけが作るものでもありません。
例えば、子どもでも大人になっても、よく忘れ物や失くし物が多い人の特徴があります。
それは、
「親が片付けや明日の用意をしていた」です。
片付けや明日の時間割や持って行く物を親がやってしまったり、手伝いすぎることで、子どもの学習の機会を取り上げてしまっているのです。
以前、こうおっしゃったママがいらっしゃいました。
子供が忘れ物をすると親が笑われますので。
気持ちは分からなくもありませんが、本当に親が大事なのでしょうか?
手を出しすぎると、子供が将来どういう大人になってしまうのか?という「子供」をメインに考えるべきではないでしょうか?
これも先ほどの宿題と同様、「なんとかなるもんだ」の甘えの構造を脳に作ってしまうのです。
明日の時間割や持って行くものは親がやってくれる
忘れ物をしても親が持ってきてくれる
子供の脳は、楽だけを覚え、いくらたっても正しい習慣を身につけようとしません。
そのまま、そのお子さんが大人になってしまうと、どういう大人になるでしょうか?
想像なさってみてほしいのです。
因みに、私の母親は宿題も明日の用意も絶対にしてくれませんでした。
忘れ物を学校に持ってきてくれるなんて、とんでもありません ^^
母親の教えはこうでした。
- 自分のことは自分で済ませる
- 自分のミスは自分で解決する
- 忘れて怒られていらっしゃい
- 忘れて恥をかいてきなさい
- 1度やったことは2度としない
「二度ある事は三度ある」
私の場合は、2度あることは三度も四度もある。
だから、2度とあってはいけないと教えられました。
自分でやってみたけど、それでもできない時には助け船を出してくれました。
命や危険にかかわること以外は、安易に手を出さない母親でした。
母親なりに心を鬼にして、我が子に学習の時間を作ってくれていたのだと思います。
早め派とギリギリ派の子どもは親の子どもの時と同じという結果も

さらに、恐ろしい調査結果もでています。
親が子どもの時にどうしていたかが、今の自分の子供と同じ状況になっているという結果です。
子どもの時に「ギリギリ派」だった親は、わが子も同じように「ギリギリ派」になっている傾向にあります
これは遺伝や血液型が原因ではありません ^^
「子は親を見て育つ」と昔から言います。
親がいつも日々の暮らしの中で、モノ事をどう解決しているのかを子供は見て真似をしているということですね。
子供に「早く、おもちゃをかたづけなさい!」と怒っていながら、自分も脱いだ服を椅子や床に置きっぱなし。
「明日の用意ができてないから忘れ物をするのよ!」って注意してるけど、自分も朝バタバタと走り回っている。
これでは全然説得力がないし、子どもは親もそうなんだからとコピーをしても当たり前ですよね。
片づけも、「あとまわし」「先送り」にしてしまう「甘えの構造」ができてしまいます。

私が同居している伯母は、とにかく「あとかたづけ」が苦手です。
特に、使った物を「つい置き」「ポイ置き」「ちょっと置き」する癖が治りません。
これまでに財布だけでも3回失くしたことがあります。
その都度、「私はここに置いてたんだけど」と言い訳をします。
「おかしいな、財布はどこに行ったんだろう?」
「誰が持って行ったんだろう?」
財布は自分でどこかに行くことはありません。
誰が持って行った?って言われたら、私が疑われている気にもなってしまいます。
だけど、神様は優しいので、ある日財布を見つけてくれるのです ^^
「ほら、ここにあるよ」って。
財布が見つかった伯母は、「見つかってよかった~!」と喜びます。
こうして、失くした財布が見つかることは良かった事なのですが、伯母の脳には「なんとかなった」の甘えの構造を作ってきたのです。
だから、今でも物をどこでもポイって置く癖は全然治りません。
何度も同じ過ちを繰り返す人の事を「お前も懲りないやつだな~」って言いますよね。
「とんでもないことをしてしまった」レベルが大きい程、「なんとかなった」時の快感は大きくなります。
誰でも自分のことは可愛いです。
でも、「自分を甘やかす」ことと勘違いをしてはいけないと思います。
特に、失くし物や忘れ物は自分だけじゃなくて、周りの人にも迷惑や不快感を与えてしまうものです。
せめて、自分の物は自分で管理する習慣は身につけておくのが、大人のマナーだと思います。
「かたづけ」「しまう」は、どちらも終わらせる、完了させるという意味です。
「かたづけ」のことを、物を「しまう」とも言ったりしますよね。
では、「かたづけ」や「しまう」の、そもそもの意味をご存知でしょうか?

言葉には語源があります。
- かたづけの語源は「かたをつける」
(方を付ける) - しまうの語源は「終う」
(一般的には仕舞うと書く)
「この問題にそろそろ方を付けよう」と言ったり、「この女はどっちのものか方を付けよう」と言ったりします(笑)
物を「しまう」は、一般的には「仕舞う」と書きますが、本来は「終う」なのです。
そのため、「早く宿題をして終い(しまい)なさい!」と言いますよね。
さらには、「早く宿題を片づけて終いなさい!」と言っても違和感がないでしょ?
つまり、「片づけ」と「終う」は、どちらも何かのモノ事を完了させるという意味なのです。
物事は全てに「はじまり」と「おわり」があります。
このブログは書き始めて、永遠に書き続けることはありません。
もうすぐ終わりの文章を書きます。
仕事だって、食事だって、映画やドラマも、電話や会話も、遊びやスポーツだって。
服を着るという「はじまり」があれば、脱ぐという「終わり」があるはずです。
本や雑誌を読むという「はじまり」があって、読み終えるという「終わり」があります。
だけど、こうした物事の本当の「終わり」は、元にもどすという「片づけ」であることを多くの人が忘れています。
今の日本の家の多くが物で散らかっているのは、この「片づけ」という「終わり」が完了できていないからです。
つまり、片づけができていないのは、物事の「かたがついていない」「しまう」が未完了という状態です。
今日、お話ししている宿題をあとまわしや先送りにしてしまう癖が身についてしまうと、それは宿題だけにとどまらず、物事すべてを「方を付けられない」、「終えない」中途半端な生き方にもつながってしまうことになるということをお伝えしたかったのです。
お子さんの宿題が終わっていないのは親として気になるでしょうね。
手伝ってやらなければと親の方が焦るでしょうね。
だけど、時には鬼になって、愛のムチも必要ではないでしょうか?
親が恥ずかしいとかではなく、親として将来のわが子の行く末を考えるなら、今どうすればいいのかを考えてみることが大切だと思います。
手を出しすぎない
口も出しすぎない
見守るという姿勢こそが、我が子をたくましい大人に導いていくことかもしれません。
夏休みの「早め派」「ギリギリ派」よりも「コツコツ派」の方がベスト

ちゃんと自分で宿題を終わらせていた子供は、さらに2パターンに分かれます。
- さっさと早目に終わらせた
- コツコツと終わらせた
どちらも自分でちゃんと済ませていたので素晴らしいです。
ただ、優劣をつけるつもりはありませんが、あえて言うなら「コツコツ」が望ましいです。
あくまでも社会人として、どちらの経験をした方が望ましいかという点からです。
社会人としてだけではなく、子どもが中学、高校、大学と成長していく過程で、勉強、スポーツ、趣味、遊びが多種多様になり、スケジュールもハードになってきます。
「コツコツと」を身につけた人の方が、自己管理力が高いという調査結果が出ています。
物の整理や片づけ、掃除においても、この「コツコツ」が最も重要なのです。
脳科学者の茂木先生によると、多くのリバウンドに共通した原因は「一気に大きな変化を望んだ」ことらしいのです。
ダイエットも一気に体重を落としたい、痩せたいという気持ちは当然誰でも持ちます。
家や部屋を早くキレイにしたいという気持ちも同じです。
脳は短時間に一気に大きな変化がおこるのを嫌う傾向があるそうです。
「一気に大きな変化」は危険だと感知してしまうからだそうです。
危険を感知した脳は、元に戻そうと指令を出します。
これが、いわゆるリバウンドのはじまりです。
これは、人間の祖先の恐竜の時代に宇宙からの巨大な隕石でほとんどの生命が死滅してしまったことが原因になっているとも言われています。
つまり、ある日突然大きな変化がおこってしまったことで「死」を経験した遺伝子が、今でも脳に生き残っているからかもしれないからだそうです。
私のお客様には一気に物を整理したり、捨てたりしないで下さいとアドバイスしてきました。
だけど、中には早くスッキリキレイの結果を見たいと一気にやられた人もいました。
その方は結果的には、「引越し疲れ」ならぬ「片づけ疲れ」を引き起こし、しばらく休養を要してしまいました。
そして、その間に気持ちやモチベーションが萎えてしまい、次第にリバウンドしかけてしまい、サポートに伺ったことがあります。
一方で、多くの人はコツコツを守っていただいたお陰で、今でもスッキリキレイな暮らしを維持なさっています。
宿題も同じ早目に終わらせる場合でも、とにかく闇雲に一気にするのではなく、スケジューリングや目標設定が重要です。
例えば、お盆は田舎に遊びに行くので、それまでにドリル系は済ませておく。
自由研究は田舎で昆虫採集をしてまとめるといった感じです。
そういう私ですが、毎年唯一ギリギリだったのが「読書感想文」でした。
本を読むのが苦痛ではなかったのですが、それを読んだ感想を文字にするのが苦手というか嫌だったのを覚えています。
そのトラウマなのか、今は漫画でさえ読むのが苦手です ^^;
まとめ|物事には「はじまり」と「終わり」があります。
「終わり」があってはいけないのは「恋愛」だけかもしれませんね。
ただ、人生にも「はじまり」と「終わり」は必ずあります。
だからこそ、毎日を、今日という一日をいかに楽しく、愉快に、幸せに生きるかが最も大切なことではないでしょうか?
物事をあとまわし、先送りにしても、その時間はあなたの人生と云う時間から引き算されることはありません。
逆に、「モノを捜す」とか、「余計に片づけが大変になる」といった時間の足し算がおきてしまうだけです。
今、やるべきことは今すぐ。
時間がかかることはコツコツと。
お子さんをお持ちの方は、今のうちに子どもと、こうしたことも大人として親としてしっかり話をしてみてはいかがでしょうか。
そして、あなたの「かたづけ」や「しまう」を子供は常に見ている、見られているという意識も忘れないでくださいね。
ブログ著者 ロハスカタス 整理ist佐藤亮介のセミナー・講座・サポートのご案内
下記のページをご参照ください。
モノ屋敷だった私が「スッキリ・キレイ整活」を実現できたノウハウを無料で購読できます。捨てられない人、散らかし癖のある人に必ずお役にたてる私からの毎朝のメッセージです。